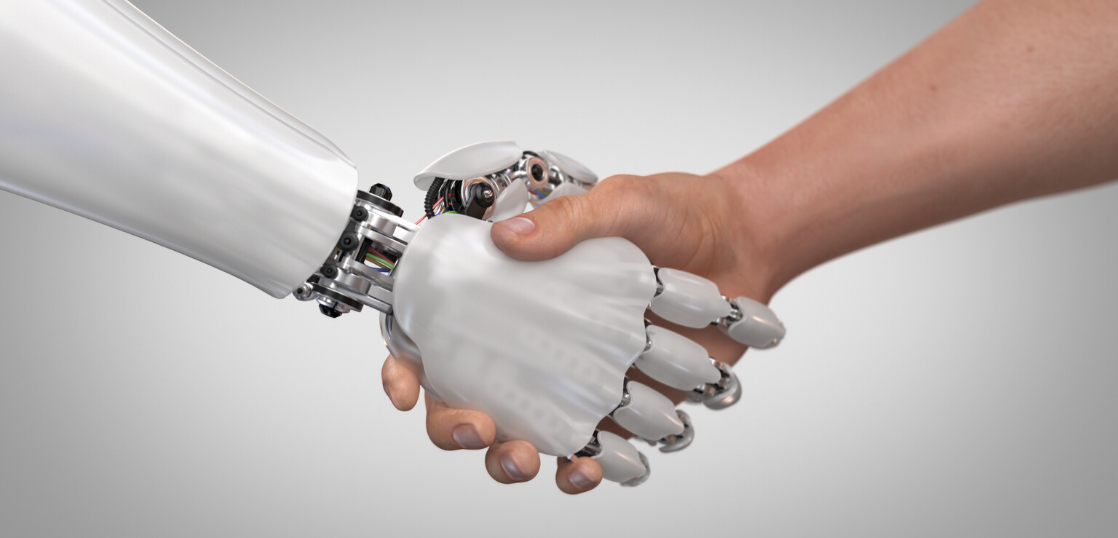「AIの民主化」時代の企業内研究開発
「AIの民主化」は、「AIブームの終焉」と共に語られる終着点の一種であった。「AIの民主化」の時代を特徴付けているのは、何よりも、「誰もが一定程度はAIを扱える」という大衆化された状態である。「AIの民主化」以降、もはや「AI」についての専門知識には、希少価値が伴わなくなる。(『「AIの民主化」時代の企業内研究開発: 深層学習の「実学」としての機能分析』本文より)
深層学習の「実学」としての機能分析
深層学習の利活用を自己目的化させる「AIブーム」は終焉を迎えました。今我々は、「AI」や深層学習の機能を冷徹に分析する機会を得ています。本来、「問題」を特定しない限り、深層学習や「AI」の問題解決策としての機能を理解することはできないはずです。株式会社Accel Brainは、現実の「問題」とその解決策として機能するアルゴリズムをセットで把握する問題志向型の機能主義的な方法に準拠した上で、深層学習や「AI」に関する理論とその実用の双方を重視した「実学」を実践します。
アルゴリズムのオープンソース開発
統計的機械学習、深層強化学習、敵対的生成ネットワーク、ニューラルネットワーク言語モデル、金融ファイナンス、行動経済学などの理論に準拠した独自アルゴリズムをオープンソースで提供することで、低コストで素早いアルゴリズム設計の概念実証や研究開発を支援しています。
アルゴリズムのAPI開発
自然言語処理やマルチエージェントシステムなどの独自アルゴリズムを利用したWebアプリケーションの開発者や、機械学習を「ノーコード(NoCode)」として機能的に利用したいユーザーを対象に、独自アルゴリズムをフリーミアムのAPIやオープンAPIとして提供しています。